
ホームページのCSSの編集について。ホームページのCSSを編集する方法としては、テキストエディタによる編集でCSSプロパティを編集し、FTPソフトによるダウンロード・アップロードを行うのが一般的です(ホームページ編集ソフトを利用することもあります)。CSSファイルとしてではなく、<head>内に<style>が挿入され、インラインスタイルとして、スタイルが指定されている場合があります。この場合は、HTML内の該当箇所を編集します。FTPでCSSファイルをダウンロードする場合のほか、ファイルマネージャ上で対象CSSファイルをダウンロードする場合もあります。また、WordPress等のCMSでは管理画面内のテーマ編集等でCSS編集を行います。
ホームページ(ウェブサイト)の外観はスタイルシート・CSSで設定されています。ホームページ修正のうちWebデザイン面の修正・調整はこのCSS編集で行います。なお、ホームページによっては複数のCSSで外観を設定している場合もあります。
CSS編集の基本的な手順

サイト・ホームページのCSS編集の基本的な手順は、FTP等で編集対象CSSファイルをダウンロードし、ローカル環境でテキストエディタを用いてCSSファイルを修正編集します。そして編集が完了した後は、対象CSSファイルをサーバーにアップロードします。
WordPressなどのCMSではブラウザ上でCSSを編集することができます。また、ブラウザを用いてサーバーのファイルマネージャ上で直接編集できる場合もあります。
<head>内に<style>が挿入され、インラインスタイルとしてスタイルが指定されている場合や、HTMLタグに「style=””」が挿入され、スタイルが要素に直書きされている場合があります。この場合は、HTML内の該当箇所を編集します。
CSS編集を行う際には、以下のポイントを押さえると、運用やSEO面でのリスクを減らせます。
まず、コードの整理です。不要なプロパティや重複した記述を削除し、コメントを活用して編集箇所を明示します。特に大規模サイトでは複数人が編集に関与するため、どこを変更したかを明確に残しておくことが後の保守性向上につながります。
次に、セレクタの命名規則を統一することです。BEM(Block Element Modifier)などの命名規則を用いることで、CSSが肥大化しても構造を把握しやすくなり、他の担当者が編集する際も誤解を防ぐことができます。
さらに、レスポンシブ対応を意識することも重要です。スマートフォンやタブレットでの表示に対応するため、メディアクエリを活用して画面サイズに応じたスタイルを設定します。適切なレスポンシブデザインはモバイルフレンドリー評価に影響し、SEO上のメリットも大きいです。
CSS編集とユーザー体験・SEOの関係
CSS編集は単に見た目を整えるだけではありません。可読性や視認性の向上、ボタンやリンクの目立たせ方、重要情報の強調など、ユーザーがページを快適に利用できるようにするための重要な要素です。Googleはユーザー体験をランキング評価の一部としており、ページ表示速度やCLS(Cumulative Layout Shift)など、Core Web Vitalsへの影響もCSSに密接に関連しています。
たとえば、画像や広告のサイズをCSSで適切に指定しておけば、読み込み中にレイアウトが崩れることを防ぎ、CLSを低減できます。また、文字サイズや行間、余白の調整は、ユーザーが文章を読みやすくするための基本であり、滞在時間や直帰率にも影響します。結果として、CSS編集はSEOに直結する施策となります。
CSSの基本構成と編集

CSSの基本構造としては、適用対象のHTMLタグやid、classを記述し(セレクタ)、プロパティ指定(プロパティとプロパティ値の設定)を行います。
- セレクタ
- プロパティ
- プロパティ値
CSS(Cascading Style Sheets)は、HTMLで作成されたページにデザインやレイアウト、装飾を施すための言語です。CSSは「セレクタ」「プロパティ」「プロパティ値」の3つを基本構造としています。
セレクタはCSSの適用対象を指定する部分で、HTMLタグ、id、classを用いてターゲットを明確にします。例えば、特定の見出しだけ色を変えたい場合はidやclassを付与し、その名前をセレクタとしてCSS内で指定します。プロパティはスタイルの項目そのものであり、色やフォントサイズ、余白、配置などを指定します。プロパティ値はそのプロパティに設定する具体的な値を指します。たとえば、colorプロパティには赤や#ff0000などの値を設定し、font-sizeプロパティにはpxやemでサイズを指定します。
CSS編集は、対象となるHTMLのセレクタに対してプロパティを追加したり削除することで行います。新しいidやclassを追加する場合は、HTML側でその適用箇所を明示する必要があります。
たとえば、新しいボタンデザインを作る場合、HTMLにclass=”custom-button”を設定し、CSSで.custom-button { background-color: #ff6600; color: #ffffff; padding: 10px 20px; border-radius: 5px; }のように記述します。このようにセレクタとプロパティ値を結びつけることで、意図したデザインを正確に表示させることが可能です。
CSS編集は、対象タグやid、classへのプロパティの追加・削除などによって行います。なお、CSS編集において、新しいセレクタとしてidやclassを設置した場合は、HTML側においてその「CSS指定を適用する部分」を指定する必要があります。
編集の手順としては、まずFTPなどでサーバーからCSSファイルを取得し、テキストエディタで開きます。ファイルを上書きする前に、対象となるセレクタやプロパティの場所を確認し必要な変更を加えます。
変更が完了したら、ファイルを保存し、FTPを介してサーバー上のCSSファイルに上書きアップロードします。WordPressで子テーマを使用している場合は、子テーマのstyle.cssに追記する形で編集することが望ましいです。こうすることで、テーマのアップデートがあっても変更内容が消えず、安全に運用できます。
ダウンロードしたCSSファイルを開き、編集対象部分のCSSプロパティを編集していきます。
編集が終わった後は、テキストエディタ上でファイルを上書き保存します。
修正編集が完了したCSSファイルをFTP等でアップロードし、サーバー上のCSSファイルを上書きします。
CSS編集が反映されていない場合
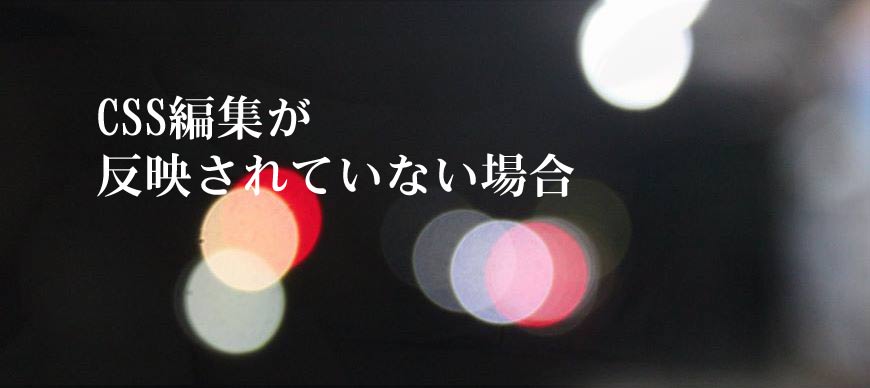
編集確認のためにページを強制更新したにもかかわらずCSS編集が反映されていない場合の要因として、CSSを上書き保存できていなかった、アップロード失敗、プロパティ設定等CSS編集にミスがあったというケースが考えられます。
編集後にブラウザ上で反映されない場合、いくつかの原因が考えられます。まず、CSSファイルの上書き保存が正しく行われていない場合です。テキストエディタの保存ミスや権限の問題でファイルが正しく書き換えられないことがあります。次に、FTPアップロードが失敗しているケースです。特にサーバー側に書き込み権限がない場合、アップロードは成功しているように見えても実際には反映されません。最後に、CSSの記述ミスも反映されない原因になります。セミコロンの付け忘れやプロパティ名のタイプミス、セレクタの誤りなどは、ブラウザがCSSを無効と判断する場合があります。
また、キャッシュが影響している場合もあります。ブラウザキャッシュやWordPressのキャッシュプラグイン、さらにはCDNキャッシュが原因で、最新のCSSが読み込まれないことがあります。この場合、スーパーリロードやキャッシュ削除、CDNのパージ機能を活用して最新状態を確認する必要があります。
CSS編集は、WordPressサイトのデザイン調整の基本であり、ユーザー体験向上やSEO評価向上にも密接に関連する重要な作業です。セレクタ、プロパティ、プロパティ値の基本構造を理解し、子テーマを用いた安全な編集、キャッシュ管理、レスポンシブ対応、パフォーマンス最適化を実践することで長期的に安定したサイト運用が可能となります。
さらに、編集履歴や命名規則の統一を行うことで、複数人での運用や将来的なテーマ更新にも柔軟に対応でき、SEOとユーザビリティの両立を図ることができます。
ホームページ修正・CSS編集

ホームページ(ウェブサイト)の更新・修正にかかる料金の価格表です。CSS編集にも対応。
長期的なホームページ運用においては、CSS編集の管理方法も重要です。子テーマを活用して安全に編集することはもちろん、編集履歴やバージョン管理を導入することで、過去の修正内容を確認し、必要に応じて元に戻すことができます。Gitなどのバージョン管理ツールを活用すれば、複数人での編集もスムーズに行え、トラブルを未然に防ぐことが可能です。
さらに、テーマのアップデート時には編集内容が反映されているか、意図せずデザインが崩れていないかを必ず確認します。特に、親テーマに変更が加わる場合、子テーマで上書きしたCSSが正しく適用されているか、セレクタやプロパティに競合がないかをテストすることが重要です。
また、サイト全体のパフォーマンスを意識することも必要です。CSSが肥大化すると読み込み速度が遅くなり、ユーザー体験を損なうだけでなく、SEO評価にも悪影響を与えます。不要なスタイルを削除し、可能であればCSSを圧縮(Minify)すること、さらにページごとに必要なCSSだけを読み込む設計を検討することが望ましいです。
