SEOとE-A-T(E-E-A-T)について。SEOの話題としてE-A-Tという評価指針があります。良質なウェブサイトを評価する基準をGoogleが独自に定めたものとなります。
E-A-Tとは、「良いコンテンツとは何か」に関するGoogleの評価指針の一つであり、Expertise(専門性)、Authoritativeness(権威性)、 Trustworthiness(信頼性)の頭文字からE-A-Tと表現されています(2022年12月よりGoogleによるとE-A-Tは、Experience(経験)を加えて「E-E-A-T」、Double-E-A-T に更新されました)。
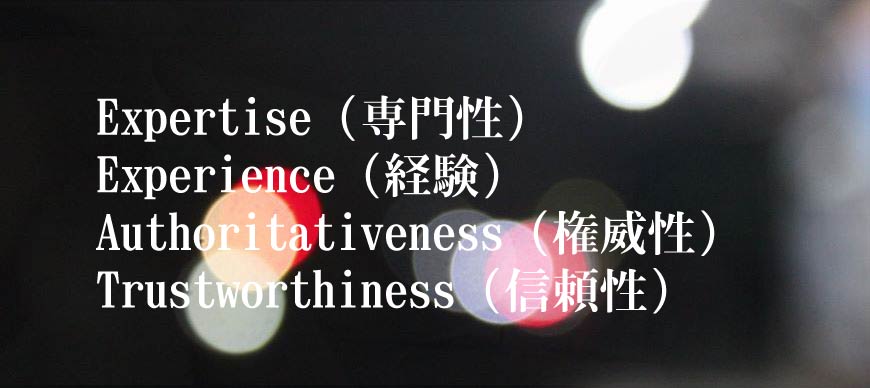
企業の公式情報において専門性、権威性、信頼性を高める要素を意識して情報を整理するに越したことはありません。(ただ、その専門性、権威性、信頼性の判断 も、あくまで数値化され予測されたものでしかありません。ある程度精度は高まりますが、絶対視することはできません)
E-A-TからE-E-A-Tへの進化
検索エンジンの進化に伴い、単純なキーワード最適化や被リンクの量だけでは、検索結果の品質を十分に保証できなくなりました。ユーザーが求める情報は、正確で信頼できるだけでなく、実際に役立ち、安心して参照できるものである必要があります。この背景から登場したのがE-A-Tという評価指標です。E-A-Tは、サイトやコンテンツの専門性、権威性、信頼性を総合的に判断する枠組みとして導入され、特に金融や医療、法律といったYMYL分野において、ユーザーにとって安全で価値ある情報を提供するための基準として機能しました。しかし、導入当初からE-A-Tは概念的な枠組みにとどまり、具体的にどのように評価されるか、どの程度サイト運営に反映されるかは明確でない部分も多く、運営者にとっては理解や対応が難しい面もありました。このような課題を背景に、ユーザー体験や実際の経験をより重視したE-E-A-Tへの進化が求められる流れが生まれていきました。
E-A-Tの登場と背景
E-A-Tとは「Expertise(専門性)」「Authoritativeness(権威性)」「Trustworthiness(信頼性)」の頭文字を取った概念で、Googleが検索品質評価ガイドラインにおいてサイトやコンテンツの品質を評価する基準として導入されました。この概念は特に医療、金融、法律など、検索結果の正確性がユーザーの判断や行動に大きく影響するYMYL(Your Money or Your Life)領域で重要視されてきました。
従来のSEO施策は主に被リンクやキーワードの最適化に偏りがちでしたが、E-A-Tは「誰が書いたか」「どの情報源に基づくか」「ユーザーにとって信頼できる内容か」といった要素を重視するもので、検索結果の品質向上を目的としたアルゴリズム評価の方向性を示す重要な指標でした。
評価の限界と課題
しかし、E-A-Tは概念的なフレームワークであるため、具体的な数値化やアルゴリズムへの直接的反映が難しいという課題がありました。専門性や権威性、信頼性は定量化できず、検索エンジンは人間の評価者によるガイドラインレビューを通じて間接的にサイト評価を行っていたため、SEO施策において「何をどう改善すれば良いのか」がわかりにくい面がありました。また、E-A-Tはページ単位での評価というよりも、サイト全体の信頼度やドメイン評価と結びついていたため、個々のコンテンツ改善が順位に直結しにくい点も指摘されていました。
ユーザー体験の重要性が高まる流れ
2020年代初頭以降、Googleは検索体験全体の質を重視する方向にシフトし、ページ単体の情報だけでなくユーザーが実際に接する体験そのものを評価指標に組み込むようになりました。モバイルフレンドリー、ページ速度、インタラクションのしやすさなど、ユーザーが快適にコンテンツにアクセスできるかどうかが検索順位に影響するようになったのです。
この流れは、単に情報の正確さや権威性を示すだけでは不十分であることを意味していました。どんなに専門性の高いコンテンツであっても、ユーザーが読みにくかったり、誤操作を誘発する構造であれば評価は下がり得ます。この背景から、E-A-Tの概念に「Experience(経験)」を加えた評価基準が導入されることになりました。
E-E-A-Tへの進化
2022年にGoogleは、検索品質評価ガイドラインでE-A-Tを拡張し、「E-E-A-T」と表記するようになりました。新たに加わった「Experience(経験)」は、コンテンツを作成した人が実際にそのテーマに関して経験を有しているかどうかを評価する指標です。例えば旅行サイトであれば、現地での体験をもとに書かれた記事は単なる情報の引用記事よりも価値が高いと判断されます。
この変更により、E-E-A-Tは単なる権威や信頼性だけでなく、実体験や実務経験に裏付けされたコンテンツをより高く評価する仕組みになりました。結果として、ユーザーにとって有益でリアルな情報が検索結果で優先される方向にアルゴリズムが調整されたのです。
E-E-A-Tの実務への影響
E-E-A-Tの導入により、Web運営者やSEO担当者は、専門的知識や権威性を示すだけでなく、実際の経験や体験を含めたコンテンツ作りが重要になりました。単なる引用やまとめ記事よりも、自身の体験や実務に基づいた情報提供が検索上位化につながる傾向が強まっています。また、E-E-A-Tはページ単位だけでなくサイト全体の評価とも結びつくため、信頼性の高い情報提供や正確な著者情報、透明性のある運営体制も重要視されるようになりました。
さらに、ユーザー体験を高める施策、例えばページ読み込み速度の改善、適切な内部リンク構造、視覚的な見やすさ、スマートフォン対応なども、E-E-A-T評価に間接的に影響することが明らかになっています。単にSEO対策を施すのではなく、コンテンツとユーザー体験の両面を最適化することが求められる時代になったのです。
WebマーケティングとE-E-A-T ホームページ制作タイプの違いによるSEOの力
現代のWebマーケティングにおいて、単なる「集客」や「アクセス数の増加」はもはや第一目標ではありません。本質的な目的は、いかに企業としての信頼を醸成し、競合他社とは異なる文脈で語られる存在になるかという「ブランドの定着」にあります。つまり、検索エンジン上で見つけてもらうだけでなく、「見つけられたあと、どう印象づけるか」こそがWebマーケティングの本丸です。Webマーケティングの世界では、信頼とは単に「真面目に見えること」ではなく、「情報の一貫性」「企業としての思想の明瞭さ」「問題提起と解決策の提示力」によって育まれます。つまり、どのような言葉で語るか、どのような順番で訴求するか、そしてどのような語調で感情に訴えるかがブランドの構成要素です。コンテンツの質と信頼性を測るうえで、検索エンジンは「専門性・権威性・信頼性(E-E-A-T)」という評価軸を導入しています。これはGoogleのアルゴリズムに組み込まれている概念であり、単にキーワードを盛り込んだだけのページでは上位表示されにくくなっている現代のSEO事情を象徴しています。
このE-E-A-Tの観点から見た場合、サブスクリプション型ホームページは致命的に弱点を抱えています。なぜなら、専門的な情報や企業独自のノウハウを深く発信するための自由度が乏しく、テンプレートの範囲を超えた表現が難しいからです。結果として、「どこにでもある会社のどこにでもあるホームページ」として処理されてしまい、検索アルゴリズムからもユーザーからも見放される可能性が高まります。
つまり、表層だけ整った情報ではなく、「どのような背景と想いから、そのサービスが生まれたのか」という文脈ごと伝える表現設計が可能なのは、自由度の高い納品型ホームページだからこそなのです。そこには、テンプレートでは到底表現できない企業の「体温」が宿ります。信頼は一朝一夕には築けません。しかし、確かな文脈と情報の一貫性、表現の独自性をもって語るホームページは、徐々に「読まれるページ」から「信じられるページ」へ、さらに「期待される企業」へと導いてくれます。これこそがWebマーケティングのもたらす真の価値であり、その土台を整える手段として納品型ホームページは極めて理にかなった選択肢です。
