
サブスクホームページの利用の注意点・デメリットについて。ホームページ制作・作成サービスの中にはサブスクホームページ(サブスクリプション型ホームページ、月額制)があります。一般のホームページ制作サービスと比較して、制作の初期コストが低いため、失敗して別のものに切り替える時に切り替えやすい(最低契約期間の設定がある場合もあります)というような特徴があります。
サブスクホームページ(サブスクリプション型ホームページ、月額制)とは、初期費用が0円や数万円程度で、その後の月額費用の負担だけでホームページ作成~公開、運営が可能なホームページ制作サービスです。初期費用は0円~低額でスタートすることが可能です。その後の毎月の月額費用だけでホームページ制作・運営が可能であることが特徴です。利用金体型、支払いのあり方は、初期費用が0円である場合、無料ホームページの有料プランと同様ですが、無料ホームページがすべての作業を自社対応するのに比べて、素材の提供等は必要になるものの、実際の設置設定は制作会社側が実施します。
「月々〇〇円でホームページを持てます」といった甘美な謳い文句に誘われ、サブスクリプション型ホームページの扉を開く企業は少なくありません。その気持ちはよくわかります。特に創業間もない企業や、これまでWebマーケティングに縁のなかった業種であれば、初期費用を抑えながら体裁の整ったサイトを持てるという提案は、大いに魅力的に映るでしょう。しかし、この「安く見える月額料金」というのは、いわば入口だけ磨かれた通路です。その先に何が待っているのかを見ずして飛び込むと、いつの間にか情報発信の自立性を奪われ、費用対効果の低い枠組みに縛られていくことになります。
サブスクホームページ(サブスクリプション型ホームページ、月額制)のデメリット

サブスクホームページ(サブスクリプション型ホームページ、月額制)のデメリットは単純です。ホームページの企画がお客任せで、SEOも弱く、Web集客・マーケティング効果を得にくいというのが最大のデメリットです。
費用面の支払いが楽だという点に着目して、「意味のないホームページ」を公開するだけになります。サブスクリプション型の料金体系は、月額制という「定額制の安心感」を前面に出しつつも、実態としてはサービス内容に厳しい制限が付されており、それを超える対応には「オプション」「追加費用」という名の関所が次々と設けられています。例えば、新たなページの追加、構成の変更、SEO対策の強化、スマホ表示の最適化、常時SSL対応、ブログ機能の実装など、本来Webマーケティングに不可欠な要素の多くが、追加費用として別建てになっているのです。
また、長期間運営する場合は費用も高くなります。そして、ホームページの規模を大きくしようと思うとどんどんと追加料金が必要になります。つまり、最初は安価に見える契約も、運用を本格化させようとするたびに「従量制の泥沼」に引き込まれ、気づけば月額以上の出費が常態化していきます。これでは「広告費の定額制パック」と変わらず、効果が出るか出ないかも分からぬまま一定の支払いだけが延々と続いていくことになります。
まずサブスクリプションホームページで、ホームページを安価に仕上げて公開しようという動機が、ホームページで集客をする気がないと考えざるを得ません。その場合は無料ホームページでよいのではないかと考えます。
本当にWeb集客効果を得ようと考えた場合は、SEOを含め、ホームページの入念な企画設計が必要です。
技術的に優れたWeb技術を使う必要はありませんが、ホームページの内容、中身は大切です。そして次にアクセスを獲得するということが重要です。
なるべく安く済ませようという動機自体が、ホームページを意味のないものにしてしまいます。
それならばホームページを公開する必要はありません。
一括払いの優れた本格的なホームページにあらゆる面で劣るサブスクリプション型ホームページ

サブスクリプション型ホームページの場合、提供される仕様はあらかじめ定められた範囲内に制限されていることが多く見られます。例えば、トップページのデザイン変更ができない、固定のテンプレートしか使えない、ページ数が制限されている、特定の機能(検索機能や予約システムなど)が追加できないなど、融通の利かない制約がいくつも存在します。これは、ホームページという重要な道具が「業者の管理下にある共有物」として扱われているためです。つまり、業者側の都合で効率的に提供できるように、あらかじめ型にはめられた枠組みの中に、顧客である企業の情報を流し込んでいるに過ぎません。
こうした状態では、自社の強みを的確に伝えることや、競合と差別化するための工夫がしにくくなります。仮に自社ならではの取り組みや、業界における独自性を強調したいと考えても、それを反映できる表現の場が与えられていないのです。ホームページは、単に会社の概要や業務内容を掲載する看板ではありません。それは、日々の事業活動を支える情報発信の拠点であり、商品やサービスの魅力を伝えるための柔軟な表現装置でもあります。ここで問うべきは、「そのホームページは、どこまで自社の戦略に合わせて自由に育てられるか」という視点です。
一括払い型の本格的なホームページのWebマーケティングの優位性
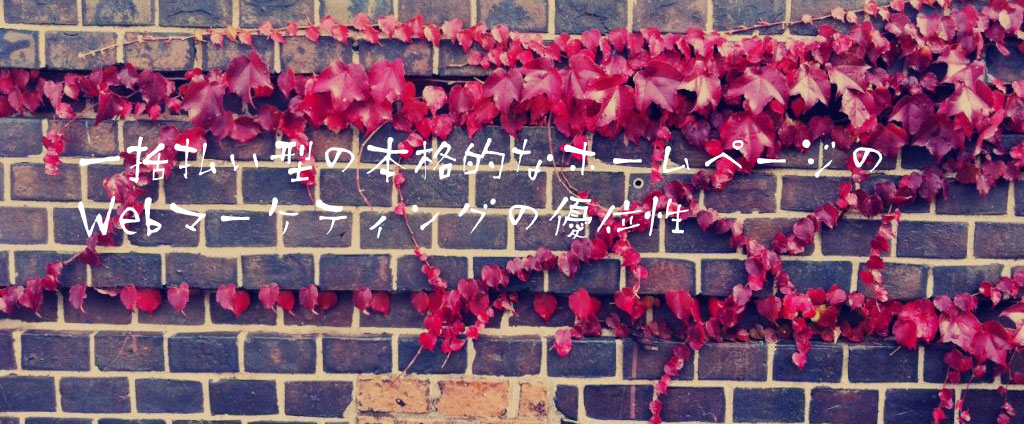
一括払い型の本格的なホームページは、自社の意図や今後の展開を見据えて、初期の段階から設計の自由度が大きく確保されています。色や構成、情報の出し方、機能の組み合わせなど、あらゆる要素が「自社専用に設計された道具」として整えられていきます。これは、既製品を借りてくるのではなく、自社の手で使いこなすための専用装備を整える感覚に近いものがあります。本格的に構築されたホームページは、その後の拡張にも柔軟に対応しやすいという特徴を持ちます。新商品を紹介するための特設ページを増設したり、動画コンテンツを組み込んだり、業界の変化に応じて構成を刷新したりと、事業の進化に寄り添うようにしてサイトを成長させていくことが可能です。これは単なる見た目の変更ではなく、Webマーケティングの実践において不可欠な「育てる余地」を持っているということを意味します。
仕様の自由度は単なる技術的な話にとどまりません。経営判断に基づく施策、たとえば商品構成の見直し、販売戦略の再設計、新規顧客層へのアプローチに合わせて、ホームページの内容や機能を自在に変えていけるかどうかは、企業の柔軟性に直結する重要な要素です。
借り物のサブスクリプション型ホームページは長期的な視野で考えると「使い込むほど不便さが露呈する道具」
つまり、借り物のサブスクリプション型ホームページは、短期間での形作りには向いているかもしれませんが、長期的な視野で考えると「使い込むほど不便さが露呈する道具」になってしまうのです。反対に、納品された持ち物としての一括払い型の本格的なホームページホームページは、最初こそ労力を伴うものの、やがて自社にとってのかけがえのない戦略的な武器となり、手を加えるたびにその機能性と価値が増していくものとなります。自社の事業は、年単位で成長し、変化していくものです。その変化に応じて、ホームページもまた柔軟に変わり続けなければなりません。自由度と拡張性を軽視した導入は、後々の手詰まりを生み出し、競合との差を広げられない足かせとなってしまうのです。
自社の意志が反映されにくいホームページはWebマーケティングを実施しにくい

サブスクリプション型のホームページは、見た目こそ立派に整っていても、その中に格納されている情報はすべて、業者側の囲いの中に閉じ込められています。データの所有権が明確に自社に帰属していないことも多く、さらに契約終了と同時にサイトが丸ごと消失する仕様になっているケースも珍しくありません。これは、いわば「砂の上に城を築いている」ようなものであり、どれほど時間をかけて情報を積み上げても、一度の契約終了で全てが白紙に戻る危うさを孕んでいます。
インターネットの世界において、企業の情報発信は単発の打ち上げ花火ではなく、継続的な投下によって初めて効果を発揮する長期戦です。つまり、一つ一つの情報が蓄積されていくことで、Webマーケティングの基盤がじわじわと強化されていきます。このとき、重要なのは「情報がどこに蓄えられているのか」、そして「誰の手でコントロールされているのか」という点です。
Webマーケティングにおいてコンテンツは「無言の営業部員」
特に、Webマーケティングにおいてコンテンツは「無言の営業部員」のような存在です。過去に書いたコラム、よくある質問のページ、導入事例の紹介、それらすべてが検索エンジン経由でのアクセスを獲得し、信頼を積み上げ、問い合わせや資料請求へと導いていきます。つまり、コンテンツの蓄積はそのまま「売上の土壌を育てる行為」であり、それが他社との競争優位をつくる武器となります。
しかしながら、サブスクリプション型の構造では、この営業装置の根幹を、他人の庭に作らされているような状態になってしまいます。長年積み上げた記事群や更新履歴が、実質的に業者のサーバーの中で管理され、自社側では自由にバックアップも取れない。このような環境では、「積むほどに依存が深まる」という逆説的な構造が成立してしまうのです。
本格的な一括払い・納品型のホームページは長期的なSEO・Webマーケティングの布石として活用可能
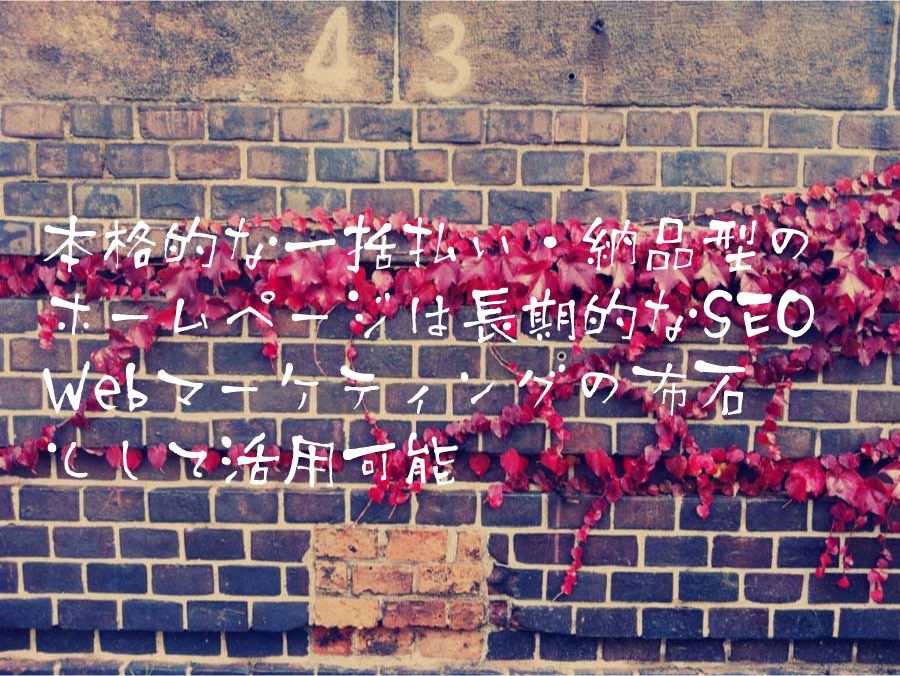
サブスクホームページに対して、本格的な一括払い・納品型のホームページでは、すべてのデータが自社に納品される前提で設計されます。ページの構造、画像、テキスト、さらには投稿したブログ記事に至るまで、その一つ一つが自社の情報資源となり、長期的なSEO・Webマーケティングの布石として活用可能です。しかも、これらの情報は検索エンジンとの関係性においても、蓄積されるほどに価値を持ちます。継続的な情報発信によってGoogleからの信頼性が高まり、自然検索での露出機会が増える。この「検索流入の土壌」は、時間をかけて育てるものであり、一朝一夕には手に入りません。つまり、一括型で構築されたホームページは、コンテンツの蓄積が可能であり、それを武器に自社独自のWebマーケティング戦略を展開していくことができるのです。
ここにおいて、「削られない情報」「持ち出せるデータ」「育てられる表現の場」がそろって初めて、Webマーケティングは企業の内部資源として機能し始めます。そして、こうした情報の累積こそが、無尽蔵の広告費に頼らない、長期的な集客体制を築く根幹となります。サブスクリプション型ホームページでは、このような「情報の自己所有性」が根本から欠落しているがゆえに、いくら更新してもWebマーケティングの成果が企業側に積み上がらないという構造的な欠点を抱えています。これはまさに、井戸を掘っても他人の土地で水を汲んでいるようなものであり、やがてその水脈が封じられたとき、何一つ手元に残らないという現実が待っています。
コンテンツの蓄積は、Web上での信頼構築、検索流入、見込み客の教育といったあらゆるWebマーケティングの活動にとっての背骨です。その背骨が業者の都合で断たれるような状態を続けていては企業が情報発信の自立性を手に入れることはできません。自社の土台の上で情報を積み上げられるか、それとも他人の土台にコンテンツを貢ぎ続けるか。Webマーケティングを本気で取り組む企業にとって、この判断は極めて重大であり長期的なマーケティング成果を左右する分岐点となります。
対して、一括払い・納品型のホームページは、確かに初期費用のハードルはあります。数十万円、場合によっては百万円以上の出費となることもありますが、それは単に「外注した成果物の代金」ではなく、「将来にわたって活用できる情報発信装置を構築するための設備投資」と捉えるべきです。
ホームページ制作費用の内訳や運用コストの安定性
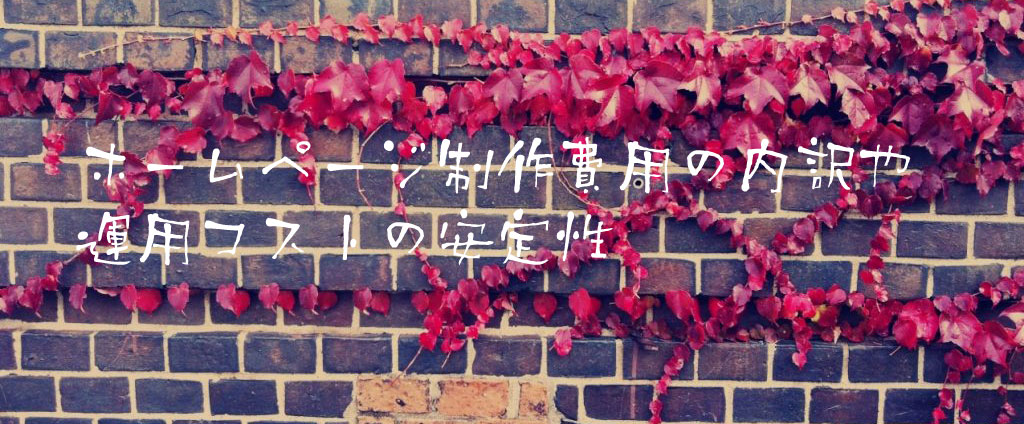
ここで注目したいのが「ホームページ制作費用の内訳」です。一括型では、設計・構築・納品・保守といった工程がすべて明示され、その後は運用にかかるコストが極端に少なくなります。つまり、初期にしっかりと作り込んでしまえば、後は自社で管理・運用できる持続可能な状態が整うのです。これは言い換えれば「一度の投資で、以後の自由が買える契約構造」であり、Webマーケティングを自前で実行しようとする企業にとって、極めて合理的な選択肢となります。コストというのは、単なる数字の比較では測れません。重要なのは、「支払った費用がどのような価値を生み、何年先までその価値が維持されるのか」という視点です。サブスクリプション型の支出は、毎月決まって出ていく消耗品費のようなものですが、一括型の支出は、蓄積型の設備投資であり、Webマーケティングの基盤づくりそのものです。
また、ホームページ運用コストの安定性という観点でも、一括払い型は優れています。月額契約のように「何もしていない月でも出費が発生する」という矛盾がなく、更新や追加を自社のペースで判断できるため、コストの調整が柔軟に行えます。これは経営的にも心理的にも大きな違いを生み出します。突発的なキャンペーンや商品ページの追加に際しても、業者に頼り切る必要がないため、対応スピードが格段に上がります。仮に10万円で作ったページが、5年間にわたって月30件のアクセスを生み、年間数件の問い合わせにつながったとすれば、それは十分すぎる成果といえるでしょう。しかもこの成果は、ランニングコストなしに、検索エンジンという巨大な流通路からの集客が継続するという、極めてコストパフォーマンスの高い構造です。
つまり、本当に比較すべきなのは「今月いくら払うか」ではなく、「3年後に何が残っているか」という問いなのです。サブスクリプション型は、「今月は安く済んだ」かもしれませんが、3年後に残るのは支払い履歴だけであり、蓄積されたWebマーケティング資源や情報発信の装置は業者側に残るか、完全に消えているかのどちらかです。表面的な金額にとらわれることなく、目に見えない「情報資源の蓄積」「発信手段の自律性」「改変の自由度」まで含めた真のコスト構造を見抜くこと。それが、Webを味方に付けて成長しようとする企業に求められる冷静かつ戦略的な判断となります。
